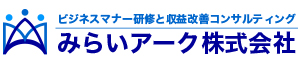はじめに
少子高齢化による後継者不足が深刻化するなか、政府の支援策等の整備も進んでいることもあり、中小企業経営者のなかでも他企業へ事業を承継するM&Aを選択するケースが増えています。
このようにM&Aを耳にしない日はないほど身近な存在となりましたが、初めてのM&Aが自社の売却となる経営者の方もいらっしゃるかと存じます。M&Aにおいてはあまり馴染みのない手続きや契約手続きを行うこととなりますので、M&Aアドバイザリー会社の協力を得て手続きを実施される方も多いかと存じます。
上場企業を含め、あまたのM&Aアドバイザリー会社が存在し、その実力も玉石混交という状況です。どのアドバイザリー企業を選ぶのかを検討する中で、手数料についても重要な比較検証材料になるかと思いますが、手数料体系も見慣れない方式を採用しているため、手数料の内容も正しく理解しておかなければ、間違った判断を下してしまうこととなります。今回は、M&A手数料についての留意点をまとめてみました。
手数料体系は大きく分けて3つ
M&Aアドバイザリー企業の報酬体系は、大きくわけて3つです。
完全成功報酬型:取引が成功した場合にのみ報酬が発生する形式です。M&Aが成功しない限り手数料は発生しませんが、取引の成約リスクをM&Aアドバイザリー会社に負わせる形式であるため、成功した場合の手数料は高額となる傾向にあります。
段階的成功報酬型:取引の進行段階に応じて報酬を支払う形式です。基本合意時、最終契約締結時、株式譲渡完了時などの段階にわけて報酬を発生させます。段階的に報酬を発生させるため、完全成功報酬と比較すると手数料は同額以下となる傾向にあります。
固定報酬型:M&Aの成否にかかわらず、月額で一定の報酬を支払う形式です。取引の成約リスクを依頼者が追う形となるため、手数料は上記2つの形式と比較し低額となります。
成功報酬体系の計算方法は、「レーマン方式」と「最低手数料」との比較
M&Aの成功報酬として一般的に使用されるレーマン方式
レーマン方式とは
レーマン方式とは、M&Aの成功報酬を算出するにあたり、取引金額に応じて段階的に計算する手法です。この方式では、取引金額の規模に応じて異なる割合の手数料が設定されており、取引規模が大きくなるほど手数料の割合が低くなるという特徴があります。
レーマン方式における手数料率の例は以下の通りです。
| 取引金額の範囲 | 手数料率 |
| 5億円まで | 5% |
| 5億円超~10億円まで | 4% |
| 10億円超~50億円まで | 3% |
| 50億円超~100億円まで | 2% |
| 100億円超 | 1% |
取引金額が70億円の場合、手数料は以下のように計算されます:
- 5億円までの部分:5億円 × 5% = 2500万円
- 5億円超〜10億円までの部分:5億円 × 4% = 2000万円
- 10億円超〜50億円までの部分:40億円 × 3% = 1億2000万円
- 50億円超〜70億円までの部分:20億円 × 2% = 4000万円
これらの金額を合計すると、手数料は2億500万円となります。
レーマン方式のメリットは、以下のとおりです。
- 透明性の確保: 手数料の計算方法が明確であり、企業は取引にかかるコストを事前に把握できます。
- インセンティブの提供: 成功報酬型であるため、M&Aアドバイザーは取引の成功に対して強いインセンティブを持ちます。
- 段階的な負担軽減: 取引金額が大きくなるほど手数料率が低くなるため、企業にとって負担が軽減されます。
一方でデメリットとされるのは以下のとおりです。
- 高額な手数料: 特に取引金額が小さい場合、手数料率が高くなるため、企業にとってコスト負担が大きくなります。
- 交渉の必要性: 手数料率や計算方法について、事前に詳細な交渉が必要となる場合があります。
レーマン方式での留意事項
レーマン方式においては、「取引金額」に手数料率をかけるという形となっています。手数料率は明確なのですが、「取引金額」の定義はM&Aアドバイザリー会社によって異なっており、必ず確認しておきたい部分となります。前述のデメリットに記載しております「交渉の必要性」はまさにこの部分なのです。
代表的な「取引金額」は「株式価値」もしくは「企業価値」のいずれかとなっています。「企業価値」を簡単に言えば、「株式価値+負債価額」となります。
例えば、株式価値1億円、負債価額4億円の会社を売却した場合、レーマン方式で算定した場合の手数料は、「株式価値」を取引金額とした場合の5百万円に対して、「企業価値」を取引金額とした場合は25百万円とかなりの差がでることになります。
また、「負債価額」の定義も「純有利子負債(有利子負債-現預金)」「有利子負債」「有利子負債+リース債務+長期未払金」など、こちらも各社によって異なっています。
そのため、「企業価値」を成功報酬における取引金額としているM&Aアドバイザリー企業の場合は、一般事例によるレーマン方式の説明(本コラムの手数料計算事例レベルの説明)だけではなく、実際に自社の貸借対照表を元に成功報酬の金額を試算してもらい、報酬金額がどれくらいになるのかしっかりと把握するようにしましょう。
なお、M&A手続きに際して実施された配当金額や役員退職金の金額を株式価値に加算して計算することが多いです。これは、オーナー企業の場合、株式譲渡よりも役員退職金で代金を受領したほうが税金を安くなるケースもあるため、退職金の支払い等を含めて株式価値としているもので、M&Aの手数料計算においては、一般的な考え方かと存じます。
最低手数料について
「自分の会社のM&Aでの取引金額は1億円くらいだから、レーマン方式での報酬は5百万円位かな」と試算された方もいらっしゃるかもしれませんが、M&Aアドバイザリー会社の報酬体系は、「レーマン方式により算定される金額もしくは最低手数料のいずれか高い方を成功報酬とする」としているケースが多いです。そして、最近はこの最低報酬の金額が高くなってきている印象があり、20百万円くらいで設定しているM&Aアドバイザリー会社もあるようです。
最低手数料の金額が上昇している要因としては、競合が激しくなるなかで優秀な人員を獲得するためのコストが高くなっていることが挙げられます。また、顧客獲得コストや買い手候補先を見つけ出すコストが高くなっていることも一つの要因でしょう。会社・自宅にうんざりするくらいM&Aをご案内するDMが届いている経営者の方もいらっしゃるかと存じますが、読まずに廃棄されているこれらDMなどのコストは、成約したM&Aの成功報酬の対価で回収することとなります。M&Aアドバイザリー企業各社が自社のより良いM&Aサービスを提供しようとしている努力の分だけ最低手数料は高くなっているのでしょう。
段階的成功報酬体系の手数料の種類
手数料の種類
段階的成功報酬体系を採用する企業の場合、以下のようなSTEPにて料金設定をしているケースが多いです。
相談料
初回の相談やアドバイスに対して支払われものですが、無料で提供される場合が多くなっています。
着手金
アドバイザリー契約を締結した際に支払う費用です。MAアドバイザリー会社は、契約を締結するまでにもコストをかけていますし、契約後には企業概要資料の作成や買い手候補先企業への打診などの作業を進めていきますので、このコストに対応するための報酬となります。
中間金
M&Aプロセスに進捗があった場合に支払われる報酬です。買い手候補先企業との面談1社ごとに中間金を設定する企業もあれば、候補先との基本合意締結をもって中間金の発生タイミングとするなど、その設定は各社によりまちまちです。
成功報酬
M&A取引が成功した場合に支払われる費用です。成功報酬の計算方法は前掲のレーマン方式を使用して算出されることが多いです。段階的成功報酬体系における最低報酬の金額は、完全成功報酬に比較すると低額となっているケースが多いようです。
また、M&Aに至らなかった場合であっても、スポンサー候補先企業との間で業務提携を行う場合もありますが、その場合の業務提携契約締結時に一定の成功報酬を求めるアドバイザリー会社もいます。
確認すべき事項
段階的成功報酬体系において、確認すべき主な事項は以下のとおりです。
相談料~中間金が成功報酬に含まれているのか含まれていないのか
成功報酬の金額からそれまでに受領している着手金・中間金の合計金額を差し引く会社と、着手金・中間金を成功報酬のなかには含まない会社とがありますので、どちらの体系となっているのか確認しましょう。
中間金の支払回数は1回のみか複数回か
基本合意の締結が中間金の発生タイミングとする契約において、基本合意を締結するたびに中間金が発生するのか、それとも一度中間金を支払えばそれ以降は発生しないのか、発生頻度を確認したほうが良いでしょう。
報酬体系をどのように選択するか
どのM&Aアドバイザリー会社にサポートを依頼するのかについては、M&A実績、信頼性、担当者との相性など重視すべき点は多くあるのですが、報酬体系だけに着目した場合、売主の「M&A実施の切迫度」により、どの料金体系がふさわしいかは変わってくるかと存じます。
何らかの理由で事業承継を早期で実施したいと考えている売主(スピード > 譲渡価格)であれば、段階的成功報酬型や固定報酬型のほうが向いており、時間をかけてでも譲渡価格を重視したい売主(スピード < 譲渡価格)であれば、完全成功報酬型のほうが向いているでしょう。
また、収益力が低い会社を売却しようとする場合、最低報酬金額の高い企業とのアドバイザリー契約ですと、買主から受領する対価だけではアドバイザリー手数料を払えないという事態が発生してしまいます。特に仲介型のM&Aアドバイザリーの場合、売主と同額の手数料を買主も負担します。最低報酬20百万円の場合は、売主・買主双方合計で40百万円の手数料の支払いが必要となります。売却企業の収益が10百万円の場合、M&A手数料を回収するために買主は4年間を要する計算となりますので、M&A実現の難易度が上がってしまいます。収益力の低い企業の売主は、最低報酬金額が高いM&Aアドバイザリー契約の締結はより慎重に検討していただけると良いでしょう。
まとめ
M&Aの手数料は、多様化しており、一度の説明ではなかなか理解しにくい部分もあるかもしれません。売主、買主、M&Aアドバイザリー会社が努力して成立したM&Aにも関わらず、最後の手数料の支払いに際してもめてしまうのは、非常に残念なことです。
予期せぬコストを避けるため、売主は手数料につき十分に確認を行い、M&Aアドバイザリー会社には説明責任と透明性が求められていると言えるでしょう。
本記事は、創業支援や資金調達に豊富な実績を持つ**みらいアーク株式会社(Mirai Arc Inc.)**の監修を受けて作成されています。みらいアーク株式会社は、創業希望者やスタートアップ企業の成長を支援するため、融資のサポートから経営コンサルティングまで幅広く対応。経験豊富なコンサルタントチームが、数多くの成功事例をもとにアドバイスを提供しています。